はじめに
SNSと音楽ストリーミングサービスが普及しつつある現代において、「定期的にリリースすること」の重要性は、もはや言うまでもないでしょう。ただし、楽曲をリリースするまでには様々な障壁が立ちはだかります。「ミックスダウン(ミックス)」「ミキシング」はそんな大きな障壁の代表的な1つ。このアーティストガイドの編集部にも現役バンドマンがいますが、彼も「初めはそもそも何を目的とした作業かすらわかんなかった」と述べていました。
本記事は彼を中心に、アーティストガイド編集部がヒアリングした「自身でミックスまでやっているバンドマン」数人の意見をまとめた、自身でミックスをやってみたい人が最初に読む指南書。と言いつつはじめに言い訳をしておくと、ミックスに対する基本的な考え方から初心者向けの具体的な作業内容までを網羅しているつもりですが、ヌケモレや解釈違いも読む人によってはあるでしょう。そこはご容赦いただきながら、同時に「なるほど、そんな考え方もあるのか」と楽しんでほしいと思います。
願わくばこの記事が、すべての駆け出しバンドマンにとって、登れども山頂の見えないミックスダウンという山の麓とならんことを。
▼ミックスを終えて完成した音源は、1曲1,551円からチューンコアでリリース!
そもそもミックスダウンってなんだ?
まずはこの記事における「そもそもミックスダウンって何なのか」を提示しておきます。人によって考え方の異なる部分でもありますが、この記事では、ミックスダウンを「バラバラに録音・制作された音(トラック)を1つのステレオ音源に合体させること」と定義しました。
音源制作の手順は、基本的には以下の3ステップを踏みます。
ステップ | 内容 |
|---|---|
レコーディング | 各楽器の音を録音したり、ソフトウェア内で音をつくったりする。(この時の各音源を「トラック」と言う) |
ミックスダウン | 各トラックを1つのステレオ音源にまとめる |
マスタリング | 1つにまとめられた音源の最終調整をする |
マスタリングについては別の記事でマスタリングエンジニアにインタビューを行っているので、そちらをご参照ください。
レコーディングをしただけでは、録音された各トラックがどのくらいの音量でどの位置から聞こえてくるのかが決まっていないので、ミックスダウンでそれらを指定していくイメージ。ただし実は単純に音を混ぜ合わせただけだと「ギターに埋もれてボーカルに聞こえない部分があるな。でもボーカルの音量を上げると今度はギターの迫力が消えてしまうな」といったように、他のトラックと混ぜ合わせてみると各トラックの聞こえ方が変わってしまうことはよくあることです。そのための調整を行うのもミックスダウンの大きな役割の1つ。各トラックが楽曲全体の中でどのように聞こえてほしいかをデザインする、音源制作の重要なパートがミックスダウンです。
ミックスダウンの心構え
具体的な作業手順に入る前に、ヒアリングを行ったアーティストたちが自身でミックスを行う上で重要な心構えの話もしていたので、紹介しておこうと思います。これから自身でミックスを行おうという初学者の皆さんは、ぜひこの心持ちを大事にしてほしいです。
「わからないこと」は永遠にある
ミックスダウンの世界で知らなきゃいけないこと、知っておいたほうが良いことは無限と言って差し支えないほど存在します。10年以上ミックスをやっているエンジニアでも、海外の新譜を聴いて「これどうやってやってるんだ」と思うことは多々あるそうです。だからこそ重要なことは、「ミックスの全てがわかるようになったら世に出そう」などと思わないこと。実際にヒアリングしたアーティストも「初めての頃はミックスダウンでよく語られる『位相』って言葉の意味もわかりませんでしたね」と照れ笑いしていました。彼は続けてこうも言っています。
「もちろん、自分の楽曲を最高のコンディションで出したい気持ちもわかります。でも出さなければその曲の良さは誰にも伝わらない。だから、いつ至れるかわからない最高のスキルを待つのではなく、いつも『今持っている知識やスキルで、今できる最高の音源を目指す』ことが重要です。」
あなたを前に進めてくれるのは〆切
ミックスを終えて完成した音源を確認してみると、「あー、ここもうちょっとドラム大きく聞こえてほしいな」といった反省点が出てきます。それを修正し、再度完成した音源を聴くと今度は「ベースが引っ込んじゃったな、もっと出さないと」と次の反省点が出てくるものです。ヒアリングしたアーティストの1人がこんなことを言っていました。曰く「どこまで最高を突き詰めても、翌月に聴いたら反省点は必ず出る」とのこと。ミックスダウンには正解がないので、こだわろうと思えば無限にこだわるポイントを見つけられてしまいます。こだわりを突き詰めることも重要ですが、それでいつまでもリリースができないのは本末転倒です。
この対策としてヒアリングしたアーティストの多くが口を揃えて言うのは、「〆切を決める」こと。〆切までは徹底的にこだわり、〆切が過ぎたら次に進むこと。これを繰り返すことで、ミックスの腕は向上し、決められた期間の中で最高のものを仕上げられるような技術が身に付いていくのだと言います。
ミックスダウンの手順
さて、ここからはヒアリングしたアーティストたちの話をまとめた具体的なミックスダウンの手順に入っていきます。揃えるべきツールの話から実践で使える技まで紹介しているので、ぜひ自分の環境で試しながら読んでみてください。




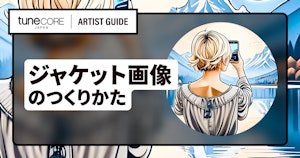




.png?width=800)
.png?width=300)






